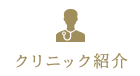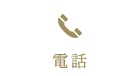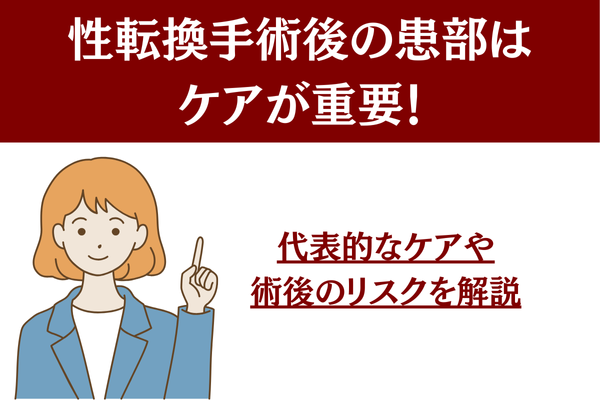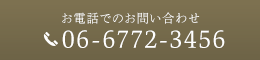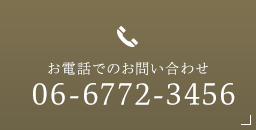「性転換手術後の患部ケアはどれほど大変なの?」
「術後にどんな副作用があるのか知りたい」
このような悩みや疑問を抱えていませんか。
生まれつき性別に対して不一致感を抱えているトランスジェンダーの方々のなかには、性転換手術を検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、手術後のケアの大変さや副作用など、体への影響をしっかり理解したうえで判断したいと思っている人は多々います。
そこで本記事では、性転換手術後の患部ケアの紹介や性転換手術後の副作用について、詳しく解説します。
この記事を読むことで性転換手術にともなう苦労やリスクがわかり、手術を決める判断材料になりますので、ぜひ最後までお読みください。
性転換手術後は患部をケアする必要がある
性転換手術後は、自己消毒や膣内洗浄など患部をケアする必要があり痛みをともないます。
また、運動制限が通常3〜4週間程度、術部の腫れと知覚異常が6か月〜3年程度つづく場合があり、これらの症状と長期間向き合う覚悟が必須です。
このように、性転換手術は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかりますが、これを乗り越えると本来のあるべき自分として生活ができます。
少しでも安心して手術にのぞめるように、事前に十分な準備と理解を深めましょう。
ここでは、性転換手術後のアフターケアの大変さについて解説していきます。
- 膣の縮小を防ぐための拡張|ダイレーション
- ホルモン治療は継続
- 尿道カテーテルは術後しばらく抜けない
一つひとつみていきましょう。
膣の縮小を防ぐための拡張|ダイレーション
男性の体から女性の体へ性別適合手術を受けた場合、膣の収縮を防ぐために「ダイレーション」と呼ばれる拡張ケアが必要になります。
ダイレーションは、つくった膣が狭くなったり閉じたりしないように、奥行きや直径を保つものです。
ダイレーションの頻度は、医療機関により異なりますが、一般的には次のようなスケジュールで行います。
| 期間 | 回数 |
|---|---|
| 術後3か月まで | 1日2回(1回につき1時間) |
| 術後4〜6か月まで | 1日1〜2回 |
| 術後6〜12か月 | 1日1回 |
| 術後1年以降 | 週に2〜3回 |
ダイレーションは、棒状の器具を膣に挿入する作業で、細いものから太いものへとサイズを段階的に大きくしていきます。
痛みをともなうこともあり、人によっては「痛みで気絶寸前だった」と表現するほど非常につらい作業なのです。
個人の体質や性転換手術の術式により、ダイレーションの必要性や頻度は異なりますが、1年以上にわたる長期のケアが必要になる可能性があることを頭に入れておきましょう。
ホルモン治療は継続
身体的治療の一つであるホルモン治療は、性転換手術後も継続して行われます。
女性ホルモンには、卵胞ホルモンである「エストロゲン」と黄体ホルモンである「プロゲステロン」があります。
手術により男性から女性に性転換しても、これらのホルモンは自然に分泌されないため、定期的に補充する必要があるのです。
ホルモン治療を続けることで、以下の効果が得られます。
- 乳房のサイズアップ
- 皮膚がやわらかくなる
- 皮下脂肪が増える
- 性欲の低下
- 筋力の低下
- 男性ホルモンの低下
ホルモン治療の頻度は、個人差がありますが、一般的には2週間〜1か月に1回の頻度で行われます。
術後もホルモンバランスが大きく崩れないようにするため、手術前と同じ量のホルモンを投与することが一般的です。
ホルモンの量を極端に減らすと無気力や頭痛、動悸などのホルモンに関連した症状が現れる恐れがあります。
反対にホルモンの量が多すぎると乳がんや子宮頸がんなど、女性特有の疾病リスクが高まります。
そのため、ホルモンは適正なバランスを保つことが大切。
ホルモン治療は身体の変化を促すだけでなく、健康を維持するためにも重要なのです。
尿道カテーテルは術後しばらく抜けない
性転換手術後はしばらくのあいだトイレに行けないため、尿道カテーテルを挿入したままにする必要があります。
性転換手術では陰茎から尿道を分離し、新たに女性器としての尿道を形成します。
そのためしばらくは自尿をするのが難しく、カテーテルを使って排尿を管理するのです。
尿道カテーテルを取り外すには、膀胱に尿をためて自分で排尿できるかどうかを医師が確認します。
膀胱に尿をため排尿する感覚を得るまでは、尿道カテーテルを外すことはできません。
術式にもよりますが、順調に回復すれば10日程度で取れることが多いでしょう。
また、数日間は排尿時に痛みを感じることもありますので、覚えておきましょう。
性転換手術後の副作用3選
性転換手術や長期のホルモン療法には、いくつかの副作用がともないます。
ここでは、代表的な副作用を3つご紹介します。
- 静脈血栓症
- 骨粗鬆症
- 乳がん
性転換手術後の副作用を知ることで手術後に起こりうるリスクを理解し、手術を受けるかどうかの判断を慎重に行えます。
それでは、順番に解説していきます。
1.静脈血栓症
女性ホルモンである「エストロゲン」は、日本血栓止血学会によると肝臓から分泌される凝固因子を増加させるため、静脈血栓症のリスクを高める恐れがあるとされています。
静脈血栓症とは、主に深部静脈に血栓と呼ばれる血の塊が形成される病気です。
一般的には片側の下肢に浮腫や痛みなどの症状があらわれます。
さらに、この血栓が血流に乗って肺に移動すると肺血栓症と呼ばれる状態になり、呼吸困難を引き起こすこともあるのです。
ホルモン治療では「エストロゲン」と「プロゲステロン」の両方を補いますが、とくに「エストロゲン」の服用により、静脈血栓症の発症リスクが1.3〜3倍に上昇します。
さらに、エストロゲンを飲みはじめてから最初の1年は静脈血栓症を発症しやすくなり、エストロゲンの含有量が多いほどリスクも高くなります。
たとえば「エチニルエストラジオール」という強力なホルモン薬は、高頻度に血栓ができやすい特徴があるため、避妊薬として使用する際には注意が必要。
患者の年齢や肥満度・喫煙の有無・家族歴などによってもリスクは異なるため、ホルモン剤の種類や期間については医師とよく相談することが重要です。
女性ホルモンの飲み薬は海外のネット通販でも比較的手に入りやすいですが、自己判断で飲むのは危険なため控えましょう。
2.骨粗鬆症
男性ホルモンがつくられる睾丸を摘出すると、体内にはホルモンがほとんどなくなります。
そのためホルモン治療を中止すると骨粗鬆症のリスクが高まります。
骨粗鬆症とは骨の量(骨密度)が減少し、骨が弱くなり骨折しやすくなる病気です。
骨は常に新しいものにつくりかえられていますが、ホルモンが不足するとこのバランスが崩れ、骨がスカスカになります。
骨は性ホルモンと密接な関係があり、男性ホルモンである「テストステロン」や、女性ホルモンである「エストロゲン」は骨の形成を促進する働きがあります。
そのため、骨の密度や量を維持するためにもホルモン治療を続けることが大切なのです。
骨粗鬆症は自覚しにくい病気で、外見からは判断が難しいです。
予防策として、定期的な骨密度の測定で骨の量を可視化していくといいでしょう。
また、小魚や乳製品などカルシウムが豊富な食材を中心に、栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。
3.乳がん
女性ホルモンの投与は、乳がんのリスクが高まりやすくなります。
乳がんは乳腺の上皮組織から発生した悪性腫瘍で、女性が患うがんのなかでもっとも多い病気です。
国立がん研究センターのがん統計によると、2020年に乳がんと診断された女性の数は91,531人でした。
乳がんと女性ホルモンの関係は密接で、女性ホルモンの一つ「エストロゲン」が乳がん細胞の増殖を促進することが知られています。
しかし、エストロゲンは女性特有の丸みのある体・美肌・骨量維持など、健康的な女性らしさを保つためには欠かせません。
そのため、適切なホルモンの投与が大切なのです。
また、乳がんのリスクを高める要因として以下が挙げられます。
- 飲酒
- 肥満
- 運動不足
- 糖尿病
がんの予防にはこれらのリスク要因に注意し、定期的に乳がん検診を受けることが重要です。
厚生労働省のがん検診データからも、2年に1回の乳がん検診を推奨しています。
性転換手術後の健康を維持するためには副作用やリスクを理解し、定期的なケアと予防を心がけましょう。
性別の変更は生殖機能を失くすことが条件
性転換手術をした多くの方は身体の女性化だけでなく、戸籍やその他の身分証明書上の性別も女性に変更したいと考えています。
それは、外見が女性であっても、身分証明書の提示によって性同一性障害が明らかになることを避けたいからです。
戸籍上の性別を変更するには、生殖機能を失くすことが条件とされています。
性別の変更を希望する場合、本人が住んでいる地域の家庭裁判所で「性別の取扱い変更の審判」を受ける必要があります。
性別変更を認められるためには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること
- 18歳以上であること
- 現に婚姻をしていないこと
- 現に未成年の子がいないこと
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
- 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
申立てには、性同一性障害であることや、治療の経過を示す医師の診断書を提出する必要があります。
審判が認められると、戸籍上の性別が変更され、新しい性別での婚姻も可能です。
性機能だけをなくす選択肢も検討できる
性転換手術後のアフターケアや副作用のリスクを考慮し、性機能だけを失くす選択肢も検討できます。
性転換手術は造膣形成による痛みや尿道カテーテルの使用など、日常生活に支障が出ます。
健康的な体に手術を施す負担や長期の入院を考慮すると、性機能だけを取り除く施術を選ぶ人も少なくありません。
そのため以下の施術もおすすめです。
| 施術名 | 効果 |
|---|---|
| 睾丸摘出 | 睾丸を摘出することでテストステロンという男性ホルモンが低下し、 心身の女性化が進む |
| パイプカット | 精管を切断することで、精巣からの精子の通り道が遮断される |
| 睾丸摘出+陰嚢切除 | 睾丸を摘出し、陰嚢を切除することで、よりすっきりとした印象を獲得する |
| ホルモン注射 | 精巣切除や豊胸術を行わずに女性化が期待できる |
クリニックや病院によって、対応できる施術は異なります。
どのような施術メニューに対応しているか、ホームページなどで確認してみましょう。
\睾丸摘出はノリス美容クリニックにご相談ください/
性転換手術はクリニックや病院でよく相談しましょう
この記事では性転換手術後の患部ケアや副作用、性別変更の条件について解説しました。
性転換手術後のアフターケアは主に以下の3つです。
- 膣の拡張を防ぐためのダイレーション
- ホルモン治療
- 尿道カテーテル
性転換手術には痛みや長期の入院、副作用などのリスクがともないます。
しかし、生まれつき性別に対して不一致感を抱えたまま生活する苦しさを解消するための、手段でもあるのです。
性転換手術の方法はさまざまなので、術式をはじめ手術による身体的変化や副作用についてクリニックや病院でよく相談してください。
自分が目指す姿をイメージしながら、自身にとって最適な治療を選択しましょう。